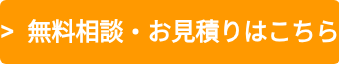【企業向け】CG・3DCG動画とは?活用シーンや制作の流れをわかりやすく解説

BtoBビジネスには、複雑で顧客に理解してもらうことが難しい製品やサービスが数多く存在します。 カタログや写真、口頭での説明だけでは十分に伝わらず、「どう動くのか」「どんな価値があるのか」を相手にイメージしてもらえない場面も少なくありません。こうした課題を解決する手段として注目されているのが、CG・3DCG動画です。
製造業の精密機器や医療分野の作用機序、ITサービスの仕組みなど、実写では見せられない内部構造や動きをリアルに再現し、誰にでもわかりやすく表現できるため、幅広い業界で導入が進んでいます。
本記事では、CG・3DCG動画の基本やメリットに加え、具体的な活用シーン、制作の流れ、効果的に活用するためのポイントを解説します。複雑な商材を「わかりやすく伝える」方法を探しているBtoB担当者は、ぜひ参考にしてください。
CG・3DCG動画とは?
ここでは、CG・3DCG動画の技術的な定義や種類の違い、BtoBビジネスでの具体的な役割について詳しく解説します。
1. CG・3DCG動画の定義
CG(Computer Graphics)はコンピューターによって生成された画像や映像を指し、その中でも立体的な奥行きや質感を再現したものを「3DCG」と呼びます。2次元のイラストやアニメーションと比べ、よりリアルで臨場感のある表現が可能で、実写映像では見せられない内部構造やシミュレーションを映像化できる点が特徴です。特にBtoBビジネスでは、製品の仕組みやサービスの動作を理解しやすく伝えるための手段として活用が広がっています。
2. 2DCGと3DCGの違い
2DCGは平面上のイラストやアニメーション表現で、情報をシンプルに整理して伝えられるのが強みです。一方で3DCGは、立体的にオブジェクトをモデリングして表現するため、実物に近いリアリティを持たせることができます。たとえば、サービスの画面操作説明であれば2DCGが有効ですが、精密機器の内部構造や医薬品の作用機序など立体的な理解が必要な場合は3DCGの方が効果的です。目的やターゲットに応じて使い分けることで、より効果的な情報伝達が可能となります。
3. BtoBにおけるCG・3DCG動画の位置づけ
BtoBの商材は専門性が高く、顧客が一度の説明で直感的に理解するのが難しいケースが多くあります。そこでCG・3DCG動画は、営業資料や展示会ブース、セミナー発表、Webサイトなど多様な場面で、複雑な情報を視覚的に整理して言葉だけでは伝わりにくい価値を体験的に理解してもらえるように「理解促進」と「差別化」を実現する役割を担います。
特に複数の関係者が関与し、意思決定までに時間を要するBtoBビジネスでは、視覚的に直感的な理解を促すCG・3DCG動画が、情報共有と合意形成のスピードアップに貢献します。
CG・3DCG動画のメリット
CG・3DCG動画は「見せたいことを自由に表現できる」という強みから、BtoBの現場で導入が進んでいます。ここでは、その具体的なメリットを3つの観点から解説します。
1. 実写では作れないものを表現できる
CG・3DCG動画の最大の強みは、実写では不可能な表現を可能にする点です。製品の内部構造や分子レベルの動き、建築物の完成予想図など、カメラでは撮影できない世界を可視化できます。視覚的なインパクトにより、見る人に強い印象を残し、製品やサービスの特長を直感的に伝えられることが大きなメリットです。
2. 複雑な仕組みや製品をわかりやすく伝えられる
BtoBビジネスの商材は、専門知識がないと理解が難しいケースが多くあります。CG・3DCG動画は、複雑な機構や仕組みをシンプルに整理し、わかりやすく解説できるため、技術に詳しくない顧客や意思決定者にも正確に価値を伝えられます。特に「どう動くのか」「どのような効果があるのか」を一目で理解してもらえることは、営業やマーケティング活動において大きな武器になります。
3. ブランド価値の向上や差別化につながる表現効果
高品質なCG・3DCG動画は、製品やサービスの魅力を伝えるだけでなく、企業そのもののブランド価値を高める効果もあります。洗練された映像表現は、先進的なイメージや信頼感を与え、競合との差別化につながります。特に展示会やオンライン広告など「第一印象」が重要な場面では、クオリティの高いCG映像がブランド力強化に直結します。
CG・3DCG動画の4つの活用シーン
CG・3DCG動画は、営業・マーケティングから教育・広報まで幅広い用途で活用できます。ここでは、BtoBビジネスで特に効果を発揮する代表的な活用シーンを4つ紹介します。
1. 展示会・イベントでの製品・サービス訴求
展示会やイベントでは、短時間で多くの来場者に製品の魅力を伝える必要があります。CG・3DCG動画を活用すれば、実機を持ち込めない大型装置や複雑なシステムでも、その仕組みや特徴をわかりやすく説明できます。リアルなアニメーションによって、来場者の理解と興味を一瞬で引きつけ、商談へのきっかけをつくることが可能です。
| 【関連記事】 |
|
展示会における動画活用の具体的な手法については、以下の記事で詳しく解説しています。 |
2. 営業・商談でのプレゼンテーション支援
営業の現場では、資料や口頭説明だけでは伝わりにくいポイントを動画で補完することができます。特に、専門性が高い製品やサービスの仕組みをCG・3DCGで表現することで、相手が抱きやすい「難しそう」という心理的ハードルを下げ、スムーズな理解を促します。また、オンライン商談でも活用しやすく、営業担当者の説明負担を軽減しながら説得力を高められる点が強みです。
3. 研修・教育でのわかりやすい説明
社内研修や顧客向けのトレーニングにおいても、CG・3DCG動画は効果的です。製品の操作手順や安全教育、研究成果の共有など、複雑な情報をわかりやすい映像で伝えることで、受講者の理解が深まり定着率も向上します。特に製造業や医療業界のように専門的な知識が求められる場面では、教育効果を大きく高められます。
| 【関連記事】 |
|
研修や教育における動画活用の具体的なメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。 |
4. ブランド訴求や企業広報での活用
コーポレートサイトや採用活動、投資家向け広報(IR)においても、CG・3DCG動画はブランドイメージを高めるツールとして活躍します。未来的で洗練された映像は「先進性」「信頼性」といった印象を強調し、企業のビジョンや理念を直感的に伝えられます。単なる製品紹介にとどまらず、企業そのものの魅力を発信する手段としても効果的です。
| 【関連記事】 |
|
ブランドイメージの向上や差別化につながる動画活用については、以下の記事で詳しく解説しています。 |
CG・3DCG動画を効果的に活用するポイント
せっかく制作したCG・3DCG動画も、使い方次第で成果に大きな差が出ます。
ここでは、動画の効果を最大化するために押さえておきたい3つのポイントを解説します。
1. 短尺版と長尺版を使い分ける
CG・3DCG動画は、その目的や使用シーンによって最適な長さが異なります。展示会やSNS広告のように「注意を引きたい」場面では30秒〜1分程度の短尺版が有効です。一方、営業プレゼンや研修など「じっくり理解を促す」場面では3分以上の長尺版が効果を発揮します。同じ素材から複数バージョンを制作し、シーンに応じて使い分けることで、投資したコンテンツを最大限に活用できます。
2. 複数チャネルで展開して接点を広げる
制作したCG・3DCG動画は、展示会や営業現場だけでなく、Webサイト、YouTube、SNS、メールマーケティングなど複数のチャネルで展開するのがおすすめです。ターゲットの接触機会が増えるほど、動画の効果も高まります。特にBtoBでは、意思決定に複数の関係者が関与するため、オンラインとオフライン両方で情報を届けることが成果につながりやすくなります。
3. 訴求ポイントを絞り込みわかりやすく伝える
CG・3DCG動画は表現の自由度が高い反面、情報を盛り込みすぎると視聴者が混乱してしまいます。伝えたいメッセージをひとつかふたつに絞り込み、映像表現もシンプルに構成することが重要です。とくにBtoBの商談や展示会のように短時間で判断される場面では、「何を伝えたいのか」が明確であるほど効果が高まります。
CG・3DCG動画の制作の流れ
CG・3DCG動画は高度な技術を要するため、制作の各工程をきちんと理解して進めることが成功のカギとなります。ここでは、一般的な制作の流れを解説します。
Step1. 企画・コンセプト設計
制作の第一歩は、目的とターゲットを明確にした企画設計です。何を伝えたいのか、誰に向けた動画なのかを整理し、ストーリーボードやラフスケッチで全体の構成を固めます。この段階で方向性を曖昧にしたまま進めると、後の工程で修正が増え、工数やコストが膨らむ原因となります。
| 【関連記事】 |
|
動画制作を成功に導くための目的設定の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。 |
Step2. モデリングとアニメーション制作
次に、実際のCGモデルを作成し、アニメーションを付けて動きを表現します。製品の形状や質感を忠実に再現するモデリングは、動画の説得力に直結する重要な工程です。さらにアニメーションで「どの部分が動くのか」「どう機能するのか」を見せることで、理解促進効果を高めます。精密さと演出効果のバランスを取りながら進めることが求められます。
Step3. 編集・仕上げと納品
モデリングとアニメーションが完成したら、テキストやナレーション、BGMを組み合わせて映像として仕上げます。全体のテンポ感や視認性を調整し、視聴者がストレスなく理解できる構成にすることがポイントです。最終的に納品形式(MP4、Web埋め込み用データなど)を決め、利用シーンに応じたファイル形式を整えます。
| 【関連記事】 |
|
動画制作全体の流れや依頼前に押さえておきたい注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。 |
制作時によくある失敗と注意点
CG・3DCG動画は映像表現の自由度が高い分、以下のような失敗が起こりやすい点に注意が必要です。
1. ターゲット設計不足
ターゲットを意識せずに制作すると、専門用語が多すぎたり、逆に情報が浅くなったりして効果が薄れてしまいます。
【対策】制作前にターゲットを明確化し、視聴者レベルに応じた専門用語の使用基準を決めておきます。
2. 工数過多による期間・予算オーバー
細部にこだわりすぎて制作期間や費用が膨らむケースが多くあります。必要な表現範囲をあらかじめ決めておくことが大切です。
【対策】「見せる必要がある部分」と「省略可能な部分」を事前の打ち合わせで認識を合わせておきます。
3. 要望の伝え方が不明確
「かっこよく」「わかりやすく」といった抽象的な要望だけを伝えると、制作会社との認識のズレが生じ、期待と違う仕上がりになってしまいます。
【対策】参考となる動画や具体的なイメージを共有し、「どんな印象を与えたいか」を明確に伝えましょう。
まとめ|CG・3DCG動画は複雑な情報を分かりやすく伝えて訴求力を高める
CG・3DCG動画は、複雑な仕組みや専門性の高い商材を分かりやすく伝える有効な手段です。展示会・商談・研修・広報など、BtoBマーケティングのさまざまな場面で理解促進やブランド価値向上に貢献します。
効果を最大化するためには、ターゲット設計、訴求ポイントの整理、活用シーンに応じた長尺・短尺の使い分け、複数チャネルでの展開などの工夫が必要です。また、制作時にはターゲット設計の不足や工数の膨らみといった失敗を避けるため、制作実績と提案力に優れた制作会社を選定することが成功につながります。
CG・3DCG動画の制作をお考えの際は、当社にお気軽にご相談ください。BtoBビジネスの特性を理解した制作チームが、効果的な映像制作をサポートします。
- トピック:
- 動画制作全般
掲載日: 2025.10.17 / 更新日: 2025.11.21