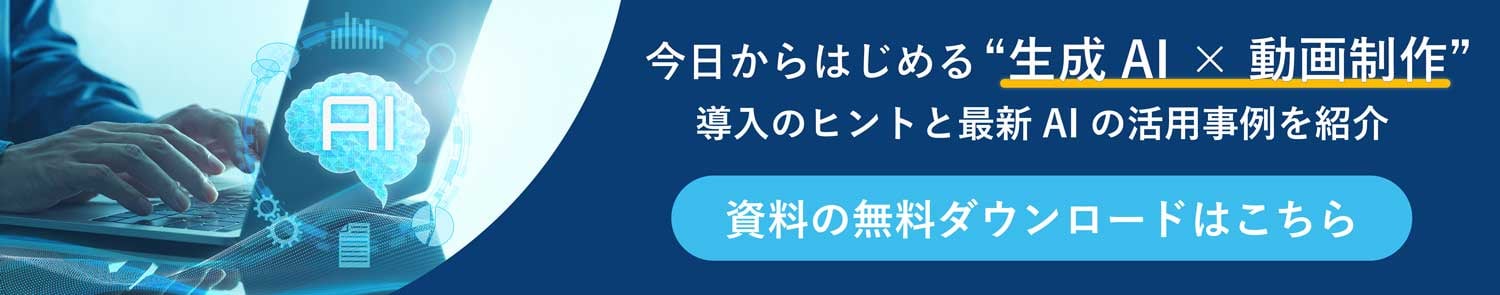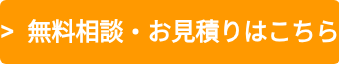【企業向け】DXが進まない企業へ──動画で組織が変わる!実現へのステップと事例紹介

デジタルトランスフォーメーション(DX)の必要性が叫ばれて久しいものの、多くの企業で、思うように進展していないのが現実です。なぜ、これほどまでに、DXの実現は困難なのでしょうか。
実は、その原因の多くは技術的な問題ではなく、組織内でのコミュニケーションや理解不足にあります。そして、この課題を解決する有効な手段として注目されているのが「動画活用」です。動画を使った情報伝達や業務改善は、それ自体がDXの一環であり、組織全体のデジタル化を加速させる起爆剤となり得るのです。
本記事では、DXが進まない根本原因を探るとともに、動画活用によるDX実現のステップと具体的なメリットについて解説します。
なぜDXが進まないのか?──多くの企業が抱える"組織の壁"
DXの推進が思うように進まない背景には、3つの大きな組織的課題があります。ここでは、号令だけでは変わらない組織の実態、現場の抵抗が生まれる理由、そして改革を成功に導く出発点について、食品製造業を例に、3つ解説します。
1. 号令だけでは人も仕組みも動かない
多くの企業でDXプロジェクトが開始される際、経営陣からの「デジタル化を進めよう」という号令が発せられます。しかし、この段階で既に多くの企業が躓いています。なぜなら、号令だけでは現場の人々が具体的に何をすべきかが見えないからです。
例えば、食品製造業で、経営陣から「工場の生産管理システム導入を進める」という方針が示されたとします。しかし、現場の作業員にとって「生産管理システム」という言葉自体が抽象的で、自分たちの日常業務にどのような変化をもたらすのかが理解できません。結果として、「また新しいシステムが導入されるのか」という受け身の姿勢に留まってしまいます。
2.「理解されないDX」が現場の抵抗を生む
DXへの抵抗が生まれる最大の要因は、その必要性や効果が現場レベルで理解されていないことにあります。経営層が描くデジタル化のビジョンと、現場が感じている日々の課題との間に大きなギャップが存在するのです。
前項の食品製造業であれば、営業部門でも同様の課題が発生しました。営業部長からは「顧客管理システムを活用して営業効率を向上させよう」という指示が出されます。しかし、ベテラン営業担当者にとって、長年の経験で培った取引先との関係性こそが財産であり、システムに顧客情報を入力することは「余計な作業」と映りがちです。特に、システムの導入効果が実感できるまでには時間がかかるため、営業チームの抵抗は強くなりました。
3. 改革の出発点は「共感と納得」
成功するDXプロジェクトに共通するのは、関係者全員が変革の必要性に共感し、その方向性に納得していることです。これは、技術的な優位性や効率化のメリットを数字で示すだけでは達成できません。
例に挙げている食品製造業では、こうした課題を受けて、まず経理部門から着手することにしました。経理担当者は、月末の売上集計作業で毎回深夜まで残業しており、家族との時間も取れない状況が続いていました。この具体的な課題に対して、「現在手作業で行っている売上集計がシステム化により自動化され、残業時間を大幅に削減できる」という身近で具体的なビジョンを示すことで、経理チーム全員の共感を得ることができました。
このように、DXが進まない企業の多くは、技術導入よりもコミュニケーションの課題を抱えています。そして、この課題を解決する有効な手段として注目されているのが「動画活用」なのです。
実は「動画活用」もDX──現場を変えるリアルなデジタル施策
動画活用は単なる情報伝達手段ではなく、業務プロセスの改善や組織変革を促すDXそのものです。ここでは、動画による業務改善の本質と、営業・マーケティング現場での具体的な活用状況、そして従来の情報伝達手段を変革する動画の力について3つの観点から解説します。
1.「動画で伝える」は業務改善そのもの
従来、企業内での情報伝達は文書や対面での説明に依存していました。しかし、この方法には多くの課題があります。文書では複雑な内容を理解してもらうのに時間がかかり、対面説明では説明者によって内容にばらつきが生じます。
一方で、動画であれば、視覚と聴覚に訴えることで理解度が格段に向上し、誰が視聴しても同じ品質の情報を得ることができます。また、一度制作すれば何度でも活用でき、時間や場所の制約を受けません。例えば操作手順を動画で制作すれば、従業員は自分の都合の良い時間に視聴でき、理解できない部分は繰り返し確認できます。
2. 営業やマーケティング現場に浸透する"動画×DX"の潮流
営業やマーケティング部門では、既に動画を活用したDXが着実に進んでいます。特に、顧客とのコミュニケーション方法や商談プロセスの変革において、動画は重要な役割を果たしています。
営業活動における代表例として、商品説明動画の活用があります。従来の営業プロセスでは、初回商談で商品の概要説明から始めることが一般的でした。しかし、事前に商品説明動画を顧客に送付することで、商談時間をより深い議論に充てることができます。
3. ツールやシステムだけがDXじゃない。伝え方の変革もDX
DXというと、AI やクラウドシステム、IoT などの先進技術の導入に注目が集まりがちです。しかし、DXとは技術導入そのものではなく、それによって業務プロセスや組織文化がどのように変革されるかにあります。
例えば、動画活用による情報伝達の変革は、組織内のコミュニケーション文化そのものを変えていきます。従来の文書中心の情報共有では、作成者の意図が正確に伝わらず、受け手によって解釈が異なるケースが頻発していました。しかし、動画を活用することで、表情や話し方、実際の作業手順など、文字では表現できない情報も含めて伝達できるため、コミュニケーションの質が大幅に向上します。
営業・マーケで動画を活用するメリットとは?
営業・マーケティング部門における動画活用のメリットを、商談効率化、時間・コスト削減、営業の標準化、マーケティングの仕組み化という4つの具体的なメリットについて解説します。
1. 商談前に視聴させることで「理解の土台」ができる
従来の営業プロセスでは、初回商談の大部分が商品・サービスの基本的な説明に費やされていました。しかし、事前に商品説明動画を顧客に送付し視聴してもらうことで、商談の質を大幅に向上させることができます。
2. 紹介・プレゼンを動画に任せて時間・コストを削減
営業活動における大きな課題の一つが、商談における時間配分です。商品説明や基本的なプレゼンテーションに多くの時間を費やすことで、顧客との関係構築や提案活動に十分な時間を割けないケースが多く見られます。商品説明や基本的なプレゼンテーションには、事前に動画を送付する、または、動画を活用し、端的に情報を伝えるなどすることで、顧客との関係構築に時間を割くことが可能になります。
3. 誰が使っても"質がぶれない"=営業の標準化
営業組織の大きな課題の一つが、営業担当者によるパフォーマンスのばらつきです。動画活用は、この課題を根本的に解決します。優秀な営業担当者のプレゼンテーションを動画として記録し、それを組織全体で活用することで、営業品質の標準化を実現できるのです。
4. 繰り返し使える=マーケの仕組み化・効率化
マーケティング活動における動画活用の最大のメリットは、一度制作したコンテンツを継続的に活用できることです。従来のイベントやセミナーは一回限りの施策でしたが、動画は何度でも繰り返し使用でき、長期的な投資効果を生み出します。
動画でDXを実現に近づける3つのステップ
動画を活用してDXを成功に導くためには、段階的なアプローチが必要です。ここでは、DXビジョンの可視化、現場の自分ごと化を促すストーリー設計、そして組織全体への浸透という3つのステップについて、具体的な実践方法を解説します。
Step1. DXの「目的と姿」を動画で可視化
DX推進の第一歩は、関係者全員が目指すべきゴールを明確に理解することです。しかし、「業務効率化」「デジタル化」といった抽象的な表現では、現場の従業員が具体的なイメージを持つことは困難です。
動画を活用することで、これらの抽象的なスローガンを具体的なビジョンとして可視化し、従業員全員が同じ理解を共有できるようになります。
例えば、「生産管理システム導入による効率化」という目標を動画で表現する場合、現在の手作業による工程管理の様子から、システム導入後の自動化された作業フローまでを時系列で見せることで、変化のイメージを明確に伝えることができます。さらに、システム導入により「残業時間が月20時間削減される」「品質管理の精度が30%向上する」といった具体的な数値目標も、グラフィックを使って視覚的に表現することで、従業員の理解と共感を促進できます。
Step2. 現場が"自分ごと化"できるストーリー設計
DXの成功には、現場の従業員一人ひとりが変革の必要性を「自分ごと」として捉えることが不可欠です。そのためには、現場の実情に即したリアルなストーリーを構築する必要があります。
動画によるストーリー設計では、従業員が日常的に直面している課題を起点とし、DXによってその課題がどのように解決されるかを具体的に描くことが重要です。
例えば、前述の食品製造業のケースでは、経理部門の月末集計作業に焦点を当てた動画を制作するというアプローチが考えられます。動画では、経理担当者が深夜まで手作業で売上データを集計している現状を映し出し、「毎月この作業で家族との時間が取れない」という従業員の実際の声を紹介するよう設計します。その後、システム導入により自動集計が可能になり、「定時で帰宅できるようになった経理担当者が家族と夕食を取る様子」を描くことで、DXの恩恵を身近な変化として実感できるストーリーに仕立てる事ができます。このように、個人の生活にまで言及したリアルなストーリーは、他部門の従業員にも「自分にとってのメリット」を想像させる効果を生み出します。
Step3. 継続活用による組織全体への浸透
DXの成功は一時的な取り組みではなく、継続的な活動によって実現されます。動画を単発的に制作・配信するのではなく、段階的な浸透プログラムの一環として計画的に活用する必要があります。
効果的な組織浸透には、フェーズ別の動画コンテンツ戦略と、継続的なフォローアップの仕組み構築が不可欠です。
たとえば段階的な動画展開のイメージとしては、第1フェーズでは経営層からのビジョン共有動画、第2フェーズでは各部門の成功事例紹介動画、第3フェーズでは従業員同士の体験談共有動画といったように、段階的にコンテンツを展開します。前述の食品製造業のケースでは、まず経理部門での成功体験を動画化することで、その効果を実感した他部門から「自分たちも取り組みたい」という声が自然に生まれるような環境づくりが期待できます。また、月次の進捗報告会では必ず動画を活用し、数値データだけでなく現場の生の声や変化の様子を継続的に共有することで、組織全体のモチベーション維持と変革意識の定着にもつながります。さらに、新入社員研修や中途採用者のオンボーディングにもDX関連動画を組み込み、企業文化として定着させる取り組みも重要です。
動画でDXを進めたい企業が注意すべき3つのポイント
動画を活用したDX推進において、注意すべきポイントを具体的な実践方法とともに解説します。
1.「誰に、何を、どう伝えるか」の整理が最重要
動画制作において最も重要なのは、制作前の戦略的な設計です。多くの企業が陥りがちな失敗は、「とりあえず動画を作れば効果的に伝わるだろう」という安易な考えで制作を開始することです。
【制作前に必ず整理すべき3つの要素】
・誰に:視聴対象者の職種、年齢層、スキルレベル、現在抱えている課題や不安など、ターゲットを具体的にする
・何を:伝えたいメッセージを一つに絞り込み、視聴後に視聴者にどのような行動を取ってもらいたいかを明確にする
・どう伝えるか:対象者に最も響く表現方法や構成を検討し、専門用語の使用レベルや動画の長さを決定する
この3つの要素が曖昧なまま制作を進めると、視聴者の心に響かない動画となり、期待した効果を得ることができません。制作開始前に関係者全員でこれらの要素を明文化し、共有することが成功の鍵となります。
| 【関連記事】 |
|
動画制作で成果を出すための目的設定については、以下の記事で詳しく解説しています。 |
2.「活用前提」で制作し、仕組みに組み込む
動画制作においてよくある失敗は、動画を作ることが目的となってしまい、実際の活用方法が後回しになることです。効果的な動画活用を実現するためには、制作段階から活用方法を具体的に設計する必要があります。
【活用を前提とした制作のチェックポイント】
・ 配信方法:社内システム、メール配信、研修プログラムなど、どこで視聴してもらうかを事前に決定
・視聴タイミング:いつ、どのような状況で視聴してもらうかを具体的に設定
・フォローアップ:視聴後の理解度確認方法や追加サポートの仕組みを構築
・動画の長さ:活用場面に応じて最適な時間設定(集合研修用、個人学習用など)
・更新・修正:内容変更時の対応方法と責任者を明確化
これらの要素を制作前に整理することで、実際に活用される動画を制作することができます
| 【関連記事】 |
|
動画制作を進める際の全体像については、以下の記事で解説しています。 |
3.「伝えるDX」に強いパートナーと組む
動画を活用したDX推進を成功させるためには、技術的なスキルだけでなく、組織変革やコミュニケーション戦略に関する深い理解が必要です。多くの企業にとって、これらの専門知識を社内だけで蓄積することは困難です。そのため、DXと動画活用の両方に精通した外部パートナーとの連携が重要になります。動画制作の技術力に加えて、組織変革の観点からDX推進をサポートできるパートナーが最適です。
【理想的なパートナーの条件】
・DXプロジェクトの推進経験:単なる動画制作だけでなく、課題解決を目的とした動画制作の実績
・業界知識:自社の業界や規模に近い案件での成功体験があること
・包括的サポート:動画活用戦略の立案から効果測定まで一貫した支援が可能であること
・継続的な関係性:単発の制作だけでなく、長期的な改善サイクルに対応できること
パートナー選定の際は、過去の実績や事例を詳しく確認し、技術力だけでなく、組織変革に対する理解度や提案力を重視することが重要です。適切なパートナーとの連携により、動画制作から活用、効果測定まで一貫したサポートを受けることができ、DX推進の成功確率を大幅に向上させることができます。
| 【関連記事】 |
|
「どの制作会社に依頼すればよいか分からない」「選び方で失敗したくない」という方は、こちらの記事も参考になります。「【企業向け】動画制作を外注するなら|失敗しない選び方と成功のコツ」 |
"動画を使うこと"から始まる、等身大のDX
DXが進まない根本的な原因は技術的な問題ではなく、組織内でのコミュニケーションや理解不足にあります。動画活用は、営業・マーケティング部門での商談効率化や標準化から始まり、目的の可視化や自分ごと化、継続的浸透を通じて組織全体のデジタル化を推進します。
当社では、単なる動画制作でなく、お客様の課題に合わせ、動画を制作しております。動画で、DXの推進にご興味があれば、ぜひ豊富な実績と専門知識を持つ当社まで、ぜひご相談ください。動画の活用戦略から動画の制作まで、ワンストップで、サポートいたします。
- トピック:
- 動画マーケティング
掲載日: 2025.09.05 / 更新日: 2025.11.21