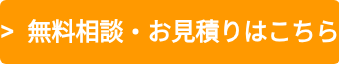【企業向け】デジタルサイネージ動画とは?効果的なコンテンツ設計や活用シーンを解説

駅や商業施設、オフィス、展示会など、さまざまな場所で大型ディスプレイに映像が流れている光景を目にする機会が増えています。この「デジタルサイネージ」と呼ばれる電子看板は、BtoB企業においても展示会で来場者の足を止める、オフィスで企業の価値を伝える、商談で製品理解を深めるなど、戦略的な活用が進んでいます。本記事では、デジタルサイネージの種類や活用メリットを整理し、成果を出すための動画制作のポイントを実践的に解説します。
「どのような場所で、どのような映像を流すと効果的なのか」を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
デジタルサイネージとは?
デジタルサイネージは、企業の情報発信を効率化し、視覚的な訴求力を高めるための重要なツールです。まずは、その基本構造について、わかりやすく解説します。
1. デジタルサイネージの定義と基本構造
デジタルサイネージとは、ディスプレイやプロジェクターなどの電子的表示機器を使い、動画や画像などのデジタルコンテンツを配信・表示する仕組みです。「電子看板」や「デジタル掲示板」とも呼ばれ、店舗・オフィス・駅・イベント会場などに設置され、販促・案内・ブランディングなど多様な用途で活用されています。
従来の紙媒体と異なり、動画や音声によって瞬時に視線を集め、短時間で強い印象を残せることが大きな特徴です。さらに、インターネット経由で表示内容をリアルタイムに更新できるため、時間帯や曜日、季節に応じた柔軟な情報発信が可能になります。
2. 従来の看板・モニターとの違い
従来の看板やポスターは、静止した一方向の情報発信が中心でした。一方、デジタルサイネージは映像・音声・文字を組み合わせた動的な表現が可能です。紙媒体では設置場所ごとに差し替え作業が必要でしたが、デジタルサイネージではインターネット経由で表示内容をリアルタイムに更新できます。時間帯や曜日ごとに表示内容を自動切替できる点も、従来メディアとの大きな違いです。
3. デジタルサイネージ が注目される理由
デジタルサイネージが多くの企業に採用されている背景には、動画コンテンツによる高い訴求力があります。動きや音を伴う映像表現は、静止画と比べて視覚的インパクトが強く、通行人や来場者の注意を瞬時に引きつけることが可能です。短時間で多くの情報を伝えられるため、展示会や店舗といった「限られた接触時間」で確実に印象を残す場面に適しています。近年では、ブランド訴求だけでなく、サービス紹介・採用広報・社内啓発など、活用の用途は広がっています。
デジタルサイネージにおける屋内・屋外の役割の違いとは
デジタルサイネージは、設置される環境によって目的や表現手法が大きく異なります。
ここでは、屋内サイネージと屋外サイネージ、それぞれの特徴・目的・活用シーンをわかりやすく解説します。
1. 屋内サイネージの特徴と活用シーン
オフィス、展示会、商業施設、ショールームなどに設置され、落ち着いた空間で視聴されることを前提としています。
ブランドムービーや製品紹介など、映像品質やデザイン性を重視した訴求に向いており、照明条件をコントロールしやすいため、細部までこだわった表現が可能です。
2. 屋外サイネージの特徴と活用シーン
街頭や駅構内、ビルボードなど、通行人の目を引くインパクト重視の設置環境で活用されます。
高輝度ディスプレイや耐候性の筐体が必要となり、昼夜や天候の変化にも対応できる設計が求められます。
新製品のプロモーションやイベント告知など、短時間で印象を残す広告施策に最適です。
デジタルサイネージの運用方法と機能の違いとは
デジタルサイネージは、映像をどのように配信・管理するかによって運用方法が大きく異なります。
ここでは、スタンドアロン型・クラウド型・インタラクティブ型という3つのタイプの特徴を比較しながら、それぞれの導入に適したシーンを解説します。
1. スタンドアロン型(単独再生型)の特徴
USBメモリやSDカードを直接挿入して動画を再生する、最もシンプルな仕組みのサイネージです。ネットワーク環境が不要なため、初期コストを抑えてすぐに導入できます。展示会や短期キャンペーンなど、一時的な利用や小規模運用に適しています。
一方で、拠点ごとにデータを手動で更新する必要があるため、複数拠点を持つ企業にはやや不向きです。
2. クラウド連携・ネットワーク型の特徴
インターネット経由で複数のサイネージを一括管理・更新できるタイプです。
本社から全国の営業所や店舗に同時配信ができ、時間帯や曜日ごとにコンテンツを自動切り替えすることも可能で、遠隔管理による運用効率の高さと情報発信の即時性が強みです。
ブランドの一貫したメッセージを全国で発信したい企業や、頻繁に更新が発生する業種に最適です。
3. タッチ式・インタラクティブ型の特徴
利用者が画面を操作して情報を閲覧できる、体験型のサイネージです。
製品検索、動画再生、アンケート入力など、双方向のコミュニケーションを通じて理解を深められます。展示会・ショールーム・採用イベントなど、“体験を通してブランドを伝える”場面に効果的です。
クラウド配信と組み合わせることで、収集したデータをマーケティングや顧客分析に活用することも可能です。
デジタルサイネージを活用する4つのメリット
デジタルサイネージは静止画やポスターとは異なり、映像ならではの表現力と、運用の柔軟性を備えています。
ここでは、企業がサイネージ動画を活用することで得られる主なメリットを4つ紹介します。
1. 視覚的インパクトで足を止めさせる
動画による動きや光の変化は、静止画よりも人の注意を引きやすく、通行人や来場者の視線を自然に誘導できます。
そのため展示会や商業施設など、限られた接触時間の中でも「まず見てもらう」可能性が高く、ブランドの第一印象を強めることが可能です。
2. 映像・音声・テキストによる多面的な訴求が可能
映像・音声・テロップを組み合わせることで、感覚的な訴求と論理的な説明を同時に行えます。製品の仕組みや導入効果など、静止画では伝えにくい情報を、ストーリー性を持たせながら直感的に伝えられるのが動画の強みです。イメージで興味を引きつけながら、具体的な情報を補足できるため、納得感のある訴求が可能です。
3. 即座に更新できる運用の柔軟性
デジタルサイネージは、動画データを更新するだけで最新情報を即時に反映できます。掲示物の差し替え作業がないためタイムラグがありません。
クラウド連携しているデジタルサイネージであれば複数拠点への一括配信も可能なため、季節のキャンペーンや新製品告知など、タイムリーな発信が容易になります。
4. ブランド訴求と集客の両立が可能
デジタルサイネージ動画は、ブランディングと販促を同時に実現できるツールです。洗練された映像で企業イメージを伝えながら、QRコードや検索ワードを表示することで、Webサイトへの誘導や資料ダウンロードといった具体的なアクションにもつなげられます。認知獲得だけでなく、次の行動を促せる点が大きな強みです。
企業がデジタルサイネージを活用する4つのシーン
デジタルサイネージは、設置場所や目的に応じて多様な活用が可能です。ここでは、企業が実際に成果を上げている代表的な4つのシーンを紹介します。
1. 商業施設や駅での広告・PR展開
駅構内や商業施設のデジタルサイネージは、不特定多数の通行人に対して短時間で認知を獲得できる広告媒体として活用されています。新商品のティザー映像やキャンペーン告知など、タイムリーな情報をインパクトのある映像で訴求することで、企業やサービスの認知拡大を図れます。
2. 展示会やイベントブースでの製品訴求
展示会では、限られたブーススペースの中で来場者の興味を引き、製品やサービスの価値を短時間で伝える必要があります。デジタルサイネージ動画を活用することで、製品の特長や導入効果を視覚的に訴求し、来場者の足を止めて担当者との商談へスムーズにつなげる導線を構築できます。
| 【関連記事】 |
|
展示会で効果的に活用できる動画の種類や制作ポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。 |
3. オフィス・ショールームでのブランド発信
自社オフィスやショールームに設置するサイネージは、来訪者に対して企業理念やブランドストーリーを映像で伝える役割を果たします。商談前の待機時間や見学ツアーの導入部分で視聴してもらうことで、企業に対する理解と信頼感を醸成し、その後のコミュニケーションを円滑にする効果があります。
4. 社内サイネージによる情報共有・教育
オフィス内の共有スペースやエントランスに設置する社内向けサイネージは、経営メッセージ・業績速報・安全啓発・社内イベント告知など、多様な情報を従業員へ届ける手段として活用されています。メールや掲示板では見逃されがちな情報も、映像として繰り返し流すことで目に触れる機会が増え、確実に情報を届けることができます。
成果を出すデジタルサイネージ動画に共通する4つの特徴
1. 設置環境(距離・音声・明るさ)に合わせた設計
効果的なデジタルサイネージ動画は、設置環境に応じた最適な設計がされています。視聴者との距離、周囲の明るさ、音声の有無など、環境条件によって適切な表現方法は大きく変わります。駅構内のような騒がしい場所では、テロップやビジュアルだけで内容が伝わる設計が必要です。一方、ショールームのような静かな環境では、ナレーションやBGMを活用した演出が効果を発揮します。視聴距離が遠い屋外サイネージでは、大きな文字と鮮明なビジュアルを優先し、細かい説明は省略する必要があります。
2. 短時間で伝わるシンプルなメッセージ
デジタルサイネージの視聴時間は、数秒から長くても30秒程度が一般的です。効果的な動画は、冒頭の3秒で視線を引きつけ、10秒以内に核心メッセージを伝える構成になっています。「何を伝えたいのか」を一つに絞り、余計な情報を削ぎ落とすことで、短時間でも記憶に残ります。たとえば、「業務効率を30%改善するクラウドツール」といった具体的なベネフィットを冒頭に提示する構成が効果的です。1本の動画につき1つのメッセージに絞ることが重要です。
3. 遠くからでも読みやすい視認性の高いデザイン
効果的なサイネージ動画は、遠くからでも読みやすいデザインになっています。視聴距離や画面サイズに応じた適切な文字サイズと、背景とのコントラストが明確に設計されており、情報を確実に届けることができます。配色は企業カラーを基調としつつ、重要な情報には目立つ差し色を活用することで、メリハリのある表現が実現されています。動きの設計もシンプルで、過度なアニメーションは避けられており、視線の流れを意識したレイアウトになっています。
4. 音声なしでも理解できる視覚表現
多くのデジタルサイネージは、音声がオフになっているか、周囲の雑音で聞き取れない環境に設置されています。効果的な動画は、映像とテロップだけで内容が完結する設計になっています。アニメーションやアイコンを効果的に使い、視覚的に情報の流れを示すことで、音声なしでも理解できる構成を実現しています。テロップは読みやすいサイズと表示時間が確保されており、重要なキーワードは繰り返し表示されることで、記憶に残りやすくなっています。
| 【関連記事】 |
|
動画制作を成功に導くための目的設定の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。 |
デジタルサイネージ動画を発注する前に確認すべき4つの項目
デジタルサイネージ動画は、制作後の配信・運用まで見据えた設計が重要です。ここでは、トラブルを防ぎスムーズに運用するための注意点を4つの視点からまとめます。
1. 設置予定のディスプレイ仕様を把握する
デジタルサイネージには、横型(16:9)、縦型(9:16)、正方形(1:1)など、さまざまなアスペクト比が存在します。制作前に必ず設置予定のディスプレイ仕様を確認し、適切な解像度とアスペクト比で動画を制作しましょう。サイズが合わない動画は、黒帯が入ったり映像が引き伸ばされたりして、見栄えが損なわれます。
また、ファイル形式についても、再生機器やCMS(コンテンツ管理システム)が対応している形式を事前に把握しておくことが重要です。運用担当者に事前に確認しましょう。
| 【関連記事】 |
|
縦型動画を効果的に制作・活用するコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。 |
2. 配信システムの仕様を事前に確認する
クラウド型サイネージを利用する場合、配信システムが対応しているファイルサイズや再生時間の上限を確認する必要があります。大容量の動画はアップロードや配信に時間がかかるため、適切な圧縮処理を施しつつ、画質を保つバランスを調整しましょう。
また、ループ再生を前提とした設計も重要です。動画の終わりと始まりがスムーズにつながるよう、映像と音楽の構成を工夫することで、違和感のない連続再生が可能になります。
3. 更新頻度と運用体制を想定しておく
デジタルサイネージの強みは、情報を柔軟に更新できる点にあります。発注前に、どのくらいの頻度でコンテンツを更新する予定か、誰が更新作業を担当するのかを想定しておきましょう。
たとえば、季節ごとのキャンペーンや新製品リリースに合わせて頻繁に更新する予定がある場合は、テロップ部分だけを差し替えられるテンプレート形式での制作を依頼することで、運用コストを抑えられます。また、動画の一部をモジュール化し、組み合わせて使えるようにしておくと、更新作業の負担を大幅に削減できます。
更新作業を社内で行うのか、制作会社に都度依頼するのかも事前に決めておくことで、適切な形式や納品仕様を制作会社に伝えることができます。
4. 見積もり・契約時に明確にすべき条件
動画制作を外注する際は、見積もり・契約段階で以下の項目を明確にしておくことが重要です。納品形式(ファイル形式・解像度・アスペクト比)、修正回数の上限、著作権やライセンスの扱い、納期とスケジュールなど、認識のズレが後々トラブルにつながりやすいポイントを事前にすり合わせましょう。
特に、納品後の軽微な修正や差し替え対応が可能かどうかは必ず確認しておくことをおすすめします。サイネージ運用では、公開後に微調整が必要になるケースも多いため、柔軟に対応できる制作会社を選ぶことが成功のカギとなります。また、使用する素材(BGM、写真、フォントなど)のライセンスについても、商用利用可能かどうか、追加費用が発生しないかを事前に確認しておきましょう。
| 【関連記事】 |
|
動画制作を外注する際の会社選びのポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。 |
デジタルサイネージ動画の成功事例
実際に企業がどのようにデジタルサイネージ動画を活用しているのか、具体的な事例を2つご紹介します。
駅構内サイネージでの縦型動画|エンカレッジ・テクノロジ株式会社様
縦型のサイネージ向けに最適化された動画を制作し、大手町駅での放映に活用された事例です。既存動画のイラスト素材を流用することでコストを抑えつつ、縦方向の動きを加えることで視聴者の目線の流れを意識した設計となっています。展示会やオフィス内での製品訴求にも展開されています。
エンカレッジ・テクノロジ株式会社様の事例について詳しくはこちらをご覧ください。
屋外環境でも視認性を確保したサイネージ動画|スーパーストリーム株式会社様
品川駅港南口の屋外サイネージでの展開事例です。通行人の多い駅構内という環境に適した短時間での訴求と、明るい屋外でも視認性の高いデザインが特徴です。イラストレーターのキャラクターを3D化し、CGや3DCGを用いて立体感のある動画を制作することで、メジャーバージョンアップを効果的にPRしています。
スーパーストリーム株式会社様の事例について詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ|デジタルサイネージ動画で企業の情報発信を「見せる」から「体験させる」へと進化させる
デジタルサイネージによる訴求は、静止画では伝えきれない情報を短時間で印象的に届けることができ、ブランディングと集客の両面で高い効果を発揮します。
重要なのは、設置環境や視聴シーンに最適化した設計を行うこと。そして、運用後も柔軟に更新できる体制を整えることです。そのためには、「誰に・どこで・何を伝えたいのか」を明確にした動画を制作し、運用まで伴走してくれる動画制作会社へ依頼することが成功への近道です。
当社は、動画制作にとどまらず、企画から完成後の活用までを一貫して支援できる体制を整えております。デジタルサイネージに最適な映像表現のノウハウと、さまざまな業種・用途での制作実績をもとに、貴社の課題に合わせた最適なプランをご提案いたします。サイネージ動画の制作や運用にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
- トピック:
- 展示会動画制作
掲載日: 2025.11.26