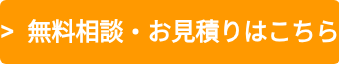【企業向け】YouTubeの再生数カウントの仕組みとは?BtoB企業が知るべき活用法を解説

YouTube動画を配信する企業にとって、再生数は最も注目する指標の一つです。しかし、「なぜ再生数が思うように増えないのか」「どのような条件で再生数がカウントされるのか」といった疑問を抱える担当者も少なくありません。
本記事では、YouTubeの再生数カウントの基本的な仕組みから、BtoB企業が実践すべき具体的な活用法まで解説していきます。YouTubeの再生数カウントの仕組みを正しく理解することで、動画マーケティング戦略にお役立てください。
| 【関連記事】 |
|
Youtubeを利用した動画マーケティング戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。 |
YouTubeの再生数はどうカウントされる?
YouTubeでは、不正な再生を除外し、実際の視聴のみを再生数としてカウントする仕組みとなっています。
ここでは、再生数として認識される条件、同一ユーザーの複数回視聴の扱い、反映タイミング、そして通常動画とショート動画の違いという4つの重要なポイントを解説します。
1. 再生数として認識される条件(視聴時間・操作方法)
YouTubeで再生数としてカウントされるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 視聴者が意図的に動画の再生ボタンをクリックする
- 一定時間以上視聴する(一般的に30秒以上とされるが、正確な秒数は非公開)※1
- 人間による実際の操作である(ボットや自動再生は除外)
30秒未満の動画の場合は、動画の大部分を視聴することが条件となります。また、自動再生やボットによる機械的な操作は、YouTubeのアルゴリズムによって検出され、再生数から除外されます。
【参考】
※1:ARTSTECHコラム 「YouTubeの再生回数が伸びないのはなぜ?」(2023年12月05日)
2. 同じユーザーの複数回視聴はどう扱われる?
同一ユーザーが同じ動画を繰り返し視聴した場合は以下の扱いとなります。
- 適度な頻度での複数回視聴は再生数としてカウントされる
- 1日に同じ動画を4~5回以上視聴すると、それ以降の視聴はカウントされない可能性がある※2
- 短時間での連続的な再生や不自然な視聴パターンは無効とされる
企業の動画マーケティングにおいては、社内での確認作業や関係者による視聴時に、同一IPアドレスからの大量アクセスが不正と判定される可能性があるため注意が必要です。
【参考】
※2:ARTSTECHコラム 「YouTubeの再生回数が伸びないのはなぜ?」(2023年12月05日)
3. 再生数が反映されるタイミングと更新頻度
YouTubeの再生数は、リアルタイムで更新されるわけではありません。
- 動画公開後の最初の数時間は、システムが正当性を検証するため実際より少なく表示される
- 再生数が301回に達した時点で詳細な検証プロセスが実行される(このため301回から増えなくなったという場合がある)※3
- 検証に問題がなければ、数時間から数日で正常な更新が再開される
- 人気動画ほど頻繁に更新される
【参考】
※3: KNOCKtimes!! 【YouTube】再生回数のカウントの仕組みについて詳しく解説!(2023年03月15日)
4. 通常動画とショート動画のカウント方法の違い
2025年4月以降、YouTubeショート動画のカウント方法に重要な変更が実施されました。※4
- 通常動画:一定時間の視聴が必要
- ショート動画:動画が表示された瞬間にカウント(TikTokやInstagramリールと同様)
このため、ユーザーが動画を最後まで視聴しなくても、再生数にカウントされる可能性が上がります。また従来の指標も「エンゲージビュー」として残されており、実際に視聴し続けたユーザー数も把握できます。BtoB企業は単純な再生数だけでなく、エンゲージビューも重要な指標として活用することが推奨されます。
【参考】
※4: ARTBRAINS 【要注意】YouTubeショート動画の再生回数カウント方法が変更!エンゲージメントビューとの違いを解説(2025年05月22日)
再生数がカウントされないケース|BtoB企業が注意すべき点
企業がYouTube動画を活用する際、再生数が正しくカウントされないケースがあることを理解しておく必要があります。ここでは、カウント対象外となる具体的なケース、ペナルティのリスク、そして企業特有の注意点を解説します。
1. 短時間視聴や自動再生はカウント対象外になる
以下の場合は再生数にカウントされません。
- 数秒程度での離脱(偶発的なクリックや誤操作と判断)
- ウェブサイトに埋め込まれた動画の自動再生
- 動画を見る意思がないのに勝手に再生される場合(例:ページを開いただけで自動的に動画が始まる)
企業サイトに動画を埋め込む際は、自動再生を避け、ユーザーの意思で再生を促すようにすることが重要です。
2. 不自然な再生増加によるペナルティとリスク
YouTubeは人為的な再生数操作に対して厳格な対応を行います。
- 短期間での急激な再生数増加の検出
- 特定IPアドレスからの大量アクセスの監視
- 最悪の場合、チャンネル停止や削除のペナルティ
過去には有名なミュージックビデオで数億回の再生数が削除された事例もあります。WEBブラウザを何度も読み込ませて再生数を増やしても、現在は再生数のカウントは行われません。企業は不正な手法に頼らず、コンテンツの質を高めることで自然な再生増加を目指しましょう。
3. 企業の内部視聴や広告流入時の注意点
企業が動画を公開する際、社内での確認視聴や広告を通じた視聴においても、YouTubeのカウントシステムに影響を与える可能性があります。以下に注意しましょう。
- 同一オフィスからの大量アクセスは不自然なパターンとして検出される可能性
- 動画公開直後の集中的な社内視聴は避ける
- YouTube広告経由の視聴は一定条件下で再生数にカウントされるが、オーガニック視聴とは特性が異なる
社内確認は少人数で時間をずらして行い、公開後は外部流入を重視した運用を心がけましょう。
YouTube動画の主要流入経路6つと活用のポイント
YouTube動画への視聴者流入には複数の経路があり、それぞれ特徴が異なります。BtoB企業が流入経路を効果的に活用するための方法を解説します。
【主要流入経路一覧】
|
流入経路 |
特徴 |
|
YouTube内検索 |
キーワード検索による能動的な情報収集 |
|
関連動画 |
視聴中の動画に関連する内容への流入 |
|
トップページ表示・おすすめ動画 |
視聴履歴に基づく自動表示 |
|
Google検索 |
検索エンジンからの直接流入 |
|
自社サイト・LP |
企業が直接コントロールできる流入 |
|
SNS・メール・営業資料 |
既存顧客・見込み客への直接アプローチ |
1. YouTube内の検索結果からの流入
YouTube内での検索流入は、視聴者が能動的に情報を求めている状態のため、BtoB企業にとって重要となる流入源の一つです。
【活用のポイント】
- 業界特有の専門用語と一般的な検索語句をバランス良く組み合わせる
- 動画タイトルや説明文に検索されやすいキーワードを配置する
- 視聴率を高めることで検索順位向上を図る
2. 関連動画からの流入
視聴した動画に関連する内容として表示される流入経路です。YouTubeのアルゴリズムにより表示されます。
【活用のポイント】
- 同業界や関連分野の人気動画との関連性を高め、一貫したテーマでシリーズ構成を作る
- 視聴者が複数の動画を連続視聴する仕組みを構築し、チャンネル全体の視聴時間を向上させる
3. トップページやおすすめ動画からの流入
YouTubeのAIが個人の視聴履歴に基づいて最適化する流入経路です。
【活用のポイント】
- 動画公開後の初期段階で高評価やコメントを多く獲得し、アルゴリズムに評価されやすい動画を制作する
- 視聴維持率を高めることで、より多くのユーザーのおすすめに表示される可能性を向上させる
4. Google 検索からの流入
Google検索結果にYouTube動画が表示されることで得られる流入です。BtoB企業にとって非常に価値の高い流入源となります。
【活用のポイント】
- 「使い方」「解説」「比較」といった情報検索ニーズに対応する動画を制作
- SEOを意識したキーワード設計により、検索意図に応える内容で上位表示を狙う
5. 自社サイトや LP からの流入
自社のウェブサイトやランディングページに動画を埋め込んだり、動画へのリンクを設置したりすることで得られる流入です。
【活用のポイント】
- 自社サイトに関連動画を配置する(例えば製品・サービスページに紹介動画を配置する)
- サイトに動画を見るメリットを記載し、視聴を促進する仕組みを作る
6. SNS・メール・営業資料からの流入
企業のSNSアカウント、メールマガジン、営業担当者が使用する資料などから動画へ誘導することで得られる流入です。
【活用のポイント】
- SNSでは動画の要点を紹介し、詳細な内容はYouTube動画で視聴してもらう導線を作る
- メール配信では動画のサムネイルとタイトルを掲載し、クリック率を向上させる
- 営業資料に動画のQRコードを掲載し、商談後に視聴してもらう仕組みを構築する
BtoB企業が再生数を正しく増やす7つの方法
BtoB企業がYouTube動画の再生数を効果的に増やすための7つの具体的な方法を解説します。
1. 信頼性を重視したサムネイル・タイトルを設計する
BtoB企業のサムネイルとタイトルは、派手さよりも信頼性と専門性を重視することが重要です。
- 検索されやすいキーワードを含め、数字で具体性を高める(例:「失敗しない5つのステップ」)
- 動画に企業ロゴを配置する
2. 動画冒頭15秒で離脱を防ぐ構成を作る
YouTubeでは動画冒頭での離脱率が全体の視聴維持率に大きく影響するため、最初の15秒が勝負です。
- 冒頭に「この動画で何が得られるか」を明確に提示し、結論や要点を先に示す
- 忙しいビジネスパーソンが短時間で価値を理解できる構成にする
3. 再生リストでジャンル・シリーズごとに動画を整理する
再生リストの活用は、視聴者の利便性向上と継続視聴促進の両面で効果があります。
- 「製品紹介」「導入事例」「運用ノウハウ」でカテゴリー分類
- 見込み客が状況に応じてアクセスしやすくする(例:勤怠管理システムを検討中の人事担当者が「勤怠管理システム導入ガイド」プレイリストで、システム選定から導入、運用開始までの流れを順序立てて視聴できる)
4. 検索されやすいキーワードを盛り込む
BtoB企業のターゲットは専門用語で検索することが多い一方、一般的な表現も使用するため、両方をバランス良く組み合わせることが重要です。
- 営業担当者やカスタマーサポートから顧客がよく使う表現を収集
- 専門用語と一般表現のバランスを取り、時事性のあるキーワードも組み合わせる
5. ショート動画で潜在層にアプローチする
60秒以内の短い動画は視聴ハードルが低いため、自社の製品・サービスをまだ知らない企業担当者にも情報を届けることができます。
- 60秒以内で業界の基礎知識や実用的なTipsを紹介
- 最後にメインチャンネルへの誘導を行い、効果的な潜在層育成を図る
6. ターゲットが視聴しやすい時間帯に投稿する
企業の担当者は通勤時間や昼休み、業務時間中に動画を視聴することが多く、一般消費者とは視聴パターンが異なります。
- 平日の朝8~9時、昼12~13時、夕方17~19時の時間帯が効果的とされる
- YouTube Studioのアナリティクス機能で自社チャンネルの視聴者がアクティブな時間帯を分析し、最適な投稿タイミングを見つける
7. YouTube アナリティクスで改善サイクルを回す
動画の視聴データを分析することで、どの部分で視聴者が離脱しているか、どのタイトルがクリックされやすいかなどを把握し、次の動画制作や既存動画の改善に活用できます。
- 視聴維持率グラフで離脱ポイントを特定し、高パフォーマンス動画の成功要因を他の動画に適用
- 月次レポート作成によりPDCAサイクルを回し続ける
再生数以外に重視すべき4つの指標
YouTube動画の成果測定において、再生数だけでは真の効果を把握できません。BtoB企業にとってより重要な4つの指標について解説します。
1. 視聴者がどこで離脱するかを示す「視聴維持率」
視聴維持率とは、動画の長さに対して平均どれくらい視聴されたかを示す割合です。例えば10分の動画で視聴維持率が60%なら、平均して6分間視聴されていることを意味します。
- 視聴維持率が高い動画は内容に興味を持たれ、YouTubeからの評価も高くなる
- 一般的には50%以上が良好とされ、この指標を改善することで動画全体の品質向上につながる※5
【参考】
※5:Team HENSHIN YouTubeの再生回数を増やすには?カウント方法や伸ばし方を登録者50万人のYouTuberが解説(2025年07月11日)
2. 見込み客の反応を測る「高評価・コメント・共有数」
エンゲージメント指標は、視聴者の動画に対する積極的な関心度を示します。
- コメント数は視聴者の深い関心度を示し、共有数は動画の実用性と拡散力を証明する
- これらの指標が高い視聴者は、より質の高い見込み客である可能性が高い
3. 次のアクションにつながる「チャンネル登録率」
チャンネル登録率は、視聴者が継続的な関係性を求めているかを示す重要な指標です。
- 登録者は新動画投稿時に通知を受け取るため、継続的なコミュニケーション機会を提供
- 長期的な営業プロセスを重視するBtoB企業にとって価値の高い資産となる
4. ビジネス成果を示す「問い合わせ・資料請求率」
最終的に重要なのは、動画視聴がビジネス成果にどれだけ貢献しているかです。
- 動画説明欄や終了画面に設置したリンクからの問い合わせ・資料請求数を測定
- どの動画が最も効果的に見込み客を獲得しているかを把握し、制作する動画の種類や内容を決定する参考にする
まとめ|BtoB企業が成果を上げるためのYouTube活用戦略を再考する
YouTubeの再生数は単純なクリック数ではなく、視聴時間や操作方法といった複数の条件を満たした場合にのみカウントされます。BtoB企業にとって重要なのは、再生数だけでなく視聴維持率、エンゲージメント指標、そして最終的なビジネス成果までを総合的に評価することです。YouTube動画を見込み客の育成から成約に至る営業プロセスの一部として位置づけることで、より大きな成果を期待できます。
当社は、動画制作にとどまらず、YouTube戦略の立案から動画制作、チャンネル運用、効果測定まで、企業の動画マーケティングを総合的に支援する体制を整えております。BtoB企業特有の課題やニーズを深く理解し、最適なソリューションをご提案いたします。YouTubeを検討中の方はぜひ一度お問い合わせください。
- トピック:
- 動画制作全般
掲載日: 2025.10.27